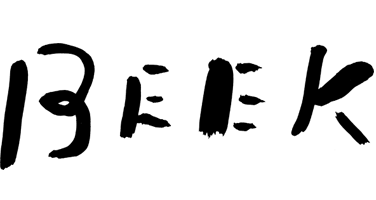その日何を食べるか、わたしはとても考える。その日が節目の日だったらなおさら。大好きなアジフライもいいし、お寿司なんかもたまには食べられたら最高だ。自然派ワインとお好み焼きのお店や、大事な日に食べたくなるイタリアンコースを出す居心地のよい古民家のお店も思い当たる。タイミングやそのときの気分が反映されるわたしのごはん選び。考えては脳内を通過していく(ように感じる)、記憶されたメニューたち。
ごはんへの執着が強くなったのは母の影響が強い。母はわたしが小さな時から、誕生日はこのお店のこのメニューを一緒に食べると決めていて、わたしが大人になってもタイミングさえあえば継続中だ。小学校の学年がひとつ上がっただけでも、学期始まりには毎回とんかつを作って祝ってくれた。
「進級なんておめでたいじゃない。鯛は母さんちょっと料理できなそうだから、学生が頑張る時に食べる定番、とんかつ食べましょう」と言って、朝からとんかつをあげてくれた。朝からとんかつを食べることに抵抗がなかったのだが、小学校高学年になって友だちに「朝からがっつり揚げ物なんて胃がもたれないの?」と言われて、ようやくとんかつは新学期の朝の定番でないことに気がついた。わたしは胃もたれもせずに、高学年になると半ば新学期のとんかつを楽しみにもしていた。母は、わたしや父の味の好み、このタイミングでこの料理が食べたいという献立をしっかりと把握し、「そろそろ冷やし中華食べたいなー」と思うとほんとうに家に帰ると冷やし中華が出てくるほどに正確だった。
母に聞くところによると、小さな頃から母の母、つまりわたしのおばあちゃんに「料理だけはしっかりできる娘にならないとだめだ」と厳しくしつけられ(ちなみにわたしは母にそんなことを言われたことはないが)、小学生の頃から包丁を持たされ一緒に料理をしていたそうだ。
社会人になりわたしも一人暮らしを始め、自分で料理をする頃にはしっかりと母やおばあちゃんの遺伝子が引き継がれていた。食べることに手を抜けないのだが、多少ずぼらな性格もあり、自己流だけど、いろいろと料理を作るようになっていた。お酒を覚えたら、このワインにはどんな料理があうかを徹底的に考えてみたり、古き良き街場の定食屋や喫茶店から、ちょっと背伸びしたレストランまで、お気に入りのお店には何度も通ってみた。もちろん季節の行事や記念日などでは、わたしなりの定番料理も完成されつつあった。
ごはんへの執着が強くなったのは母の影響が強い。母はわたしが小さな時から、誕生日はこのお店のこのメニューを一緒に食べると決めていて、わたしが大人になってもタイミングさえあえば継続中だ。小学校の学年がひとつ上がっただけでも、学期始まりには毎回とんかつを作って祝ってくれた。
「進級なんておめでたいじゃない。鯛は母さんちょっと料理できなそうだから、学生が頑張る時に食べる定番、とんかつ食べましょう」と言って、朝からとんかつをあげてくれた。朝からとんかつを食べることに抵抗がなかったのだが、小学校高学年になって友だちに「朝からがっつり揚げ物なんて胃がもたれないの?」と言われて、ようやくとんかつは新学期の朝の定番でないことに気がついた。わたしは胃もたれもせずに、高学年になると半ば新学期のとんかつを楽しみにもしていた。母は、わたしや父の味の好み、このタイミングでこの料理が食べたいという献立をしっかりと把握し、「そろそろ冷やし中華食べたいなー」と思うとほんとうに家に帰ると冷やし中華が出てくるほどに正確だった。
母に聞くところによると、小さな頃から母の母、つまりわたしのおばあちゃんに「料理だけはしっかりできる娘にならないとだめだ」と厳しくしつけられ(ちなみにわたしは母にそんなことを言われたことはないが)、小学生の頃から包丁を持たされ一緒に料理をしていたそうだ。
社会人になりわたしも一人暮らしを始め、自分で料理をする頃にはしっかりと母やおばあちゃんの遺伝子が引き継がれていた。食べることに手を抜けないのだが、多少ずぼらな性格もあり、自己流だけど、いろいろと料理を作るようになっていた。お酒を覚えたら、このワインにはどんな料理があうかを徹底的に考えてみたり、古き良き街場の定食屋や喫茶店から、ちょっと背伸びしたレストランまで、お気に入りのお店には何度も通ってみた。もちろん季節の行事や記念日などでは、わたしなりの定番料理も完成されつつあった。
今日は人生の節目、と言ったら少しおおげさかもしれない。わたしは明日、28年住んだ山梨を離れることになった。つまり、山梨でのごはんは今日を最後にしばらく食べられなれくなるのだ。もちろん近い距離なので、帰ってくればなんだって食べに行けるのだが、小学生の進級を一大イベントと捉える母に育てられたわたしは、だいたいがおおげさなのだからしょうがない。
そもそも山梨を離れる理由は単純で、3年前からお付き合いしている彼が東京に住んでいて一緒に住むことになったから。彼も地元は山梨なのだが、写真の仕事で数年前から上京していた。
わたしはなんだかんだ一大事と理由をつけて、ごはんを食べに行きたいのだ。この一大事に行くべきお店は、さんざんおいしいものを脳裏に思い浮かべたが、彼と出会った場所「珈琲専門店 ドルチェ」と決まっていた。
わたしはなんだかんだ一大事と理由をつけて、ごはんを食べに行きたいのだ。この一大事に行くべきお店は、さんざんおいしいものを脳裏に思い浮かべたが、彼と出会った場所「珈琲専門店 ドルチェ」と決まっていた。



わたしは地元の短大を出て、その後は企業に就職はせずに、そこそこ大型の地元の書店でアルバイトをはじめて、2年ほど経ってそのまま就職した。ほんとうは文章を書いて仕事がしたいと思っていたけど、田舎ではなかなか文章を書いて生計を立てることが現実的に難しかった。わたしはごはん好きに加えて、記録魔というスキルを小さい頃から備えていた。いつからかは自分でも忘れてしまったが、食べたものを落書きしたり、中学生くらいになると日記のようにその日の母の料理や友だちたちと食べた学校帰りの流行りのカフェのスイーツや店員さんの身なりや動きを観察して、夜寝る前に日記に書くという行為をずっと続けてきた。わたしの唯一の自慢、と言ってもいいかもしれない。母の料理が美味しくて、美味しいと思った理由やその日あったことの記憶とともに日記に書き記していた。高校生でパソコンを手に入れてからは、パソコンに書きためた。ブログとして誰に発信するわけでもなく、自分のために。タラタラと日々の習慣は大学を卒業するくらいまで続いた。
書店で働きだしたのは、書くことと同じくらい本を読むことも好きだったし、日々本に触れられる仕事は書くことと違って日常的に田舎にもあったし、ちょうど働きたいと思ったタイミングで書店でバイトを募集していた。最初、本が好きな人は世の中にたくさんいて、そこから本をどれだけ読んでいるかなどの基準で選ばれし人にしか書店員の仕事はできないかと勝手に想像していた。しかし、わたしはすぐにその書店に採用されたし、面接の時にどれだけの本を読んだかも特に聞かれなかった。別のバイトの子がやめてからすぐまたバイトの募集をしたけど、しばらく応募してくる人はいなかった。書店員になりたい人がこの世の中あふれているわけではないとその時知った。
書店員の仕事は重い本を何冊も持って移動するなど意外と肉体労働が多かったり、出版業界や書店営業の大変な部分が見えたと想像とは違う部分もいろいろあった。だけど、それがとても面白かった。新刊の本がいちはやく書店に並ぶのも見られるし、わたし個人的にお気に入りの本を面出しして並べた時の反応を見たり、どういった人たちが買っていくのかがわかるのは書店にいなくてはできない体験だ。
書店員の仕事は重い本を何冊も持って移動するなど意外と肉体労働が多かったり、出版業界や書店営業の大変な部分が見えたと想像とは違う部分もいろいろあった。だけど、それがとても面白かった。新刊の本がいちはやく書店に並ぶのも見られるし、わたし個人的にお気に入りの本を面出しして並べた時の反応を見たり、どういった人たちが買っていくのかがわかるのは書店にいなくてはできない体験だ。



わたしは就職して3年経った頃にこのドルチェに出会い、月に2、3回は必ずドルチェに寄って本を読むようになっていた。仕事の休日の昼下がりの日もあれば、仕事終わりの夜に寄ることもあった。ドルチェはわりと夜遅く(22時)まで開いている。喫茶店やコーヒーショップがわりと少ない山梨で、夜遅くまでやっていること自体ありがたい。いわゆるチェーンのコーヒーショップも山梨に増えてきたけけれど、本を読みたいと思える空間はわたしにとってはドルチェ一択だ。
昭和55年にオープンしたドルチェの店内は、今もその時の雰囲気を纏ったまま続いている。雑誌や新聞も充実しているところや店内のクラシックのBGMが「どうぞゆっくりしていってください」というマスターの配慮を感じるのだ。カウンター奥に見えるカップ&ソーサは200種類を超え、マスターがお客さんの雰囲気や服装などに合わせて選んでくれているそう。今日はどんな柄のカップで来るのか、毎回密かに楽しみにしている常連さんも多いはず。
私は読書目的がほとんどだったので、お店にはほぼ一人で訪れていた。たまに同じ職場のバイトの女の子と来ることもあったけれど、そんな時も決まって道路側の席がわたしの定番席だった。
ドルチェにはカウンターもあって、そこは常連さんの定席のように思えていたので、まだまだ私なんかが近寄れるものではないと勝手に思っていた。しかし、喫茶店のカウンターに対する憧れはとてもある。いつかはカウンターでマスターに「いつものください」と言える日を、私は心のどこかで待ち望んでいる。そんな気持ちをマスターに見透かされたのか、ドルチェに通いだして半年くらい経った頃には、マスターが会計の時に「今日は何を読んでたの?」とか「この本がおすすめだよ」と気さくに話しかけてくれるようになった。
そしてわたしの人生を左右することになる「ドルチェ読書会」のお誘いの声がかかるまで、そう長くはかからなかった。人生を左右する、と言うのはまたも大げさな言いぶりだ。しかし、ドラマにあるような異性との出会い方をしたことなんてなかった私からしたら、今の彼と出会うことになった読書会は人生を左右した。
昭和55年にオープンしたドルチェの店内は、今もその時の雰囲気を纏ったまま続いている。雑誌や新聞も充実しているところや店内のクラシックのBGMが「どうぞゆっくりしていってください」というマスターの配慮を感じるのだ。カウンター奥に見えるカップ&ソーサは200種類を超え、マスターがお客さんの雰囲気や服装などに合わせて選んでくれているそう。今日はどんな柄のカップで来るのか、毎回密かに楽しみにしている常連さんも多いはず。
私は読書目的がほとんどだったので、お店にはほぼ一人で訪れていた。たまに同じ職場のバイトの女の子と来ることもあったけれど、そんな時も決まって道路側の席がわたしの定番席だった。
ドルチェにはカウンターもあって、そこは常連さんの定席のように思えていたので、まだまだ私なんかが近寄れるものではないと勝手に思っていた。しかし、喫茶店のカウンターに対する憧れはとてもある。いつかはカウンターでマスターに「いつものください」と言える日を、私は心のどこかで待ち望んでいる。そんな気持ちをマスターに見透かされたのか、ドルチェに通いだして半年くらい経った頃には、マスターが会計の時に「今日は何を読んでたの?」とか「この本がおすすめだよ」と気さくに話しかけてくれるようになった。
そしてわたしの人生を左右することになる「ドルチェ読書会」のお誘いの声がかかるまで、そう長くはかからなかった。人生を左右する、と言うのはまたも大げさな言いぶりだ。しかし、ドラマにあるような異性との出会い方をしたことなんてなかった私からしたら、今の彼と出会うことになった読書会は人生を左右した。
「ドルチェ読書会」は第3土曜日の夜に開催され、読書好きの常連さんがあつまって好きな本を薦め合うという趣旨で開催されていた。メンバーはマスターが本好きと見定めた常連さんを誘っていた。
はじめての読書会では、どの本を持って行こうかとても悩んだ。本好きが多い中で、流行りものは直球すぎて書店員という職種からも商売色が見えすぎてしまうのではないかとか、海外作家の本もいきなり斜に構えてるように見られないかとか、無駄に心配性が出てしまう。結果、そのときちょうど読み終えた最果タヒの「夜空はいつでも最高密度の青色だ」を持ち込んだ。谷川俊太郎や茨城のり子のような正統派の詩も好きだ、でもそのときのわたしには、なにか捉まえどころのない日々の心の靄を、文月悠光や最果タヒの詩で輪郭をつかもうとしていたように思える。もちろん、今思えば、だが。
読書会はわたしが思ったよりも和やかで、マスターも積極的にはじめてのわたしのことを参加者に紹介してくれた。この日の参加者は18人。こんなに人数がいるとは思わず驚いた。もっと数人の会なのかと思っていた。毎回参加者は20人から25人になることも。本が好きというだけで集まっている人たちと話すことは新鮮だった。なにせ読書という行為は一人で始まり一人で完結する。映画みたいに友人を誘って観終わってから感想を言い合うということがまずない。
4グループに分かれて好きな本を紹介しあったが、わたしのグループにいた40代後半と思われる三島由紀夫の「音楽」を持ってきたまるでその小説の中に出てきそうな艶っぽさを持ったお姉さんが、わたしの本の解説にとても興味を持ってくれた。「へー、今時の詩はこんな文体なんだね」「メンヘラって言葉できたの最近だよね?」とくったくない笑いを浮かべながら。
その後、数ヶ月後に仕事の都合がついたので2回目の参加をした。今度はたまに持ち歩くコンパクトフィルムカメラと星野道夫の「旅をする木」を持ち込んで。
「あれ、GR1だ。写真撮るんですか? ぼくも写真撮ってるんですよ」
ふと席に置いていたわたしの古臭い無骨なカメラを見て、前回は見なかった同年代に見える男性が声をかけてくれた。
「父の影響で写真が好きな程度なんですけど。そんなに詳しいとかじゃないんですよ」
「写真が好きっていちばんいいじゃないですか。本も好きじゃないと読まないでしょ?」
「まあ、はい。そうですね」
「写真が好きで本が好きなんて、いちばんバランス良い要素ですよ。ぼくは写真とプロレスと餃子だからぜんぜんバランス悪いんだよなあ」
そう言って笑っておどけた男性は、「はじめまして、ぼくは坂間です」と名乗った。ふだんは写真の仕事(まだこの当時はアシスタント)で東京にいて、今日はたまたま帰省のタイミングと重なったので参加できたのだそう。坂間さんと同じグループになり、坂間さんはポール・オースターの「ムーンパレス」を紹介した。
「ここから先、物語はだんだんこみいってくる、って書き出しがあるんですけど、ほんとうに話がこみいってきてぼくら読者を惹きつけるんですよ。最後にはもうジャイアントスイングでふりまわされて、目がまわっているうちに3カウントとられる感じなんですよ」と、まったく説得力のない説明でオースターを語るからわたしは思わず吹き出してしまった。
「新人さんバカにしてるなー」と言われ、その直後どこにあったのか一眼レフカメラをさっとかまえさっとシャッターを押し、また何事もなかったようにカメラがするすると席に消えた。たぶん5秒くらいの出来事。
なんだったんだと思っているうちに、わたしの番になり「旅をする木」の説明を始めた。
坂間さんはその後も、星野道夫さんの写真やアラスカの話、同じ雪国でもまったく違う美瑛を撮った前田真三など何人かの好きな写真家のことも教えてくれた。時折はさむ冗談がちょっとわたしにはわからないところもあったり、その違和感がとても新鮮だった。
その日の夜、帰宅するとわたしのLINEアカウントに坂間さんが例の5秒で撮影したドルチェでの写真が送られてきた。さっと撮ったようにみえたのに、しっかりとピントもあって、その時のわたしの驚いた表情がそのまま写っていた。「え、すごい。なんで」と、あの一瞬で撮れた写真の綺麗さとなんでわたしのLINEのアカウントを知っているのかという二つのなんでが現れた。
「あれか」思い当たるところは、読書会は会の終了後、全グループで紹介した本を今日とりあげた本がなんだったかわかるように写メを取り、参加できなかった読書会メンバーにもあらかじめ作られているLINEグループで共有される。つまりグループ内でLINEアカウントが共有されている。
わたしはご丁寧にLINEの表示名が本名そのままだ。間違いようがない。坂間さんはそこからたどってメッセージを送ってくれたのだろう。
ちなみに写真と一緒に「今日のわんこ」のYouTubeアドレスが記載されていた。なんか、形容しがたい顔のパグの紹介動画だった。
バカみたいって思ってまたクスクス一人で笑ってしまった。たぶん、今坂間さんに見られたらしてやったりなんだろうな、と思いながら。
オースターの小説曰く「ここから先、物語はだんだんこみいってくる」「僕の身におきたことをひとつひとつ書きつらねることはできる。でもいくら正確に詳細に綴ってみたところで、僕が語ろうとしている物語全体をカバーすることにはならないだろう」、とわたしと坂間さんのことはこの言葉で終わらせて、だいたいのことは少しこみいって、だいたいは定番の恋愛ストーリーが進んで、結果付き合うことになったと思ってもらえればいい。
そんな結末になった半年後、わたしと坂間さんははじめて二人でドルチェを訪れ付き合いだしたことをマスターに告白すると、「そんなのもう知ってるよ」とあっさりと言われ、頼んでもいないのにクリームソーダをニヤニヤしながら二つ出してくれた。読書会メンバー内ですぐに噂になり、マスターの耳にもその噂はすぐに届いていたそうだ。
後から聞いた話だが、この読書会をきっかけに結婚までたどりついたカップルもいるらしい。マスターはそのことを自分の息子、娘のように喜んでいたそうだ。それからというもの読書会に参加すると恋がうまくいくというジンクスを交えて人に紹介することもあるらしい。近いうちにわたしたちの実例も含まれるだろうな。
はじめての読書会では、どの本を持って行こうかとても悩んだ。本好きが多い中で、流行りものは直球すぎて書店員という職種からも商売色が見えすぎてしまうのではないかとか、海外作家の本もいきなり斜に構えてるように見られないかとか、無駄に心配性が出てしまう。結果、そのときちょうど読み終えた最果タヒの「夜空はいつでも最高密度の青色だ」を持ち込んだ。谷川俊太郎や茨城のり子のような正統派の詩も好きだ、でもそのときのわたしには、なにか捉まえどころのない日々の心の靄を、文月悠光や最果タヒの詩で輪郭をつかもうとしていたように思える。もちろん、今思えば、だが。
読書会はわたしが思ったよりも和やかで、マスターも積極的にはじめてのわたしのことを参加者に紹介してくれた。この日の参加者は18人。こんなに人数がいるとは思わず驚いた。もっと数人の会なのかと思っていた。毎回参加者は20人から25人になることも。本が好きというだけで集まっている人たちと話すことは新鮮だった。なにせ読書という行為は一人で始まり一人で完結する。映画みたいに友人を誘って観終わってから感想を言い合うということがまずない。
4グループに分かれて好きな本を紹介しあったが、わたしのグループにいた40代後半と思われる三島由紀夫の「音楽」を持ってきたまるでその小説の中に出てきそうな艶っぽさを持ったお姉さんが、わたしの本の解説にとても興味を持ってくれた。「へー、今時の詩はこんな文体なんだね」「メンヘラって言葉できたの最近だよね?」とくったくない笑いを浮かべながら。
その後、数ヶ月後に仕事の都合がついたので2回目の参加をした。今度はたまに持ち歩くコンパクトフィルムカメラと星野道夫の「旅をする木」を持ち込んで。
「あれ、GR1だ。写真撮るんですか? ぼくも写真撮ってるんですよ」
ふと席に置いていたわたしの古臭い無骨なカメラを見て、前回は見なかった同年代に見える男性が声をかけてくれた。
「父の影響で写真が好きな程度なんですけど。そんなに詳しいとかじゃないんですよ」
「写真が好きっていちばんいいじゃないですか。本も好きじゃないと読まないでしょ?」
「まあ、はい。そうですね」
「写真が好きで本が好きなんて、いちばんバランス良い要素ですよ。ぼくは写真とプロレスと餃子だからぜんぜんバランス悪いんだよなあ」
そう言って笑っておどけた男性は、「はじめまして、ぼくは坂間です」と名乗った。ふだんは写真の仕事(まだこの当時はアシスタント)で東京にいて、今日はたまたま帰省のタイミングと重なったので参加できたのだそう。坂間さんと同じグループになり、坂間さんはポール・オースターの「ムーンパレス」を紹介した。
「ここから先、物語はだんだんこみいってくる、って書き出しがあるんですけど、ほんとうに話がこみいってきてぼくら読者を惹きつけるんですよ。最後にはもうジャイアントスイングでふりまわされて、目がまわっているうちに3カウントとられる感じなんですよ」と、まったく説得力のない説明でオースターを語るからわたしは思わず吹き出してしまった。
「新人さんバカにしてるなー」と言われ、その直後どこにあったのか一眼レフカメラをさっとかまえさっとシャッターを押し、また何事もなかったようにカメラがするすると席に消えた。たぶん5秒くらいの出来事。
なんだったんだと思っているうちに、わたしの番になり「旅をする木」の説明を始めた。
坂間さんはその後も、星野道夫さんの写真やアラスカの話、同じ雪国でもまったく違う美瑛を撮った前田真三など何人かの好きな写真家のことも教えてくれた。時折はさむ冗談がちょっとわたしにはわからないところもあったり、その違和感がとても新鮮だった。
その日の夜、帰宅するとわたしのLINEアカウントに坂間さんが例の5秒で撮影したドルチェでの写真が送られてきた。さっと撮ったようにみえたのに、しっかりとピントもあって、その時のわたしの驚いた表情がそのまま写っていた。「え、すごい。なんで」と、あの一瞬で撮れた写真の綺麗さとなんでわたしのLINEのアカウントを知っているのかという二つのなんでが現れた。
「あれか」思い当たるところは、読書会は会の終了後、全グループで紹介した本を今日とりあげた本がなんだったかわかるように写メを取り、参加できなかった読書会メンバーにもあらかじめ作られているLINEグループで共有される。つまりグループ内でLINEアカウントが共有されている。
わたしはご丁寧にLINEの表示名が本名そのままだ。間違いようがない。坂間さんはそこからたどってメッセージを送ってくれたのだろう。
ちなみに写真と一緒に「今日のわんこ」のYouTubeアドレスが記載されていた。なんか、形容しがたい顔のパグの紹介動画だった。
バカみたいって思ってまたクスクス一人で笑ってしまった。たぶん、今坂間さんに見られたらしてやったりなんだろうな、と思いながら。
オースターの小説曰く「ここから先、物語はだんだんこみいってくる」「僕の身におきたことをひとつひとつ書きつらねることはできる。でもいくら正確に詳細に綴ってみたところで、僕が語ろうとしている物語全体をカバーすることにはならないだろう」、とわたしと坂間さんのことはこの言葉で終わらせて、だいたいのことは少しこみいって、だいたいは定番の恋愛ストーリーが進んで、結果付き合うことになったと思ってもらえればいい。
そんな結末になった半年後、わたしと坂間さんははじめて二人でドルチェを訪れ付き合いだしたことをマスターに告白すると、「そんなのもう知ってるよ」とあっさりと言われ、頼んでもいないのにクリームソーダをニヤニヤしながら二つ出してくれた。読書会メンバー内ですぐに噂になり、マスターの耳にもその噂はすぐに届いていたそうだ。
後から聞いた話だが、この読書会をきっかけに結婚までたどりついたカップルもいるらしい。マスターはそのことを自分の息子、娘のように喜んでいたそうだ。それからというもの読書会に参加すると恋がうまくいくというジンクスを交えて人に紹介することもあるらしい。近いうちにわたしたちの実例も含まれるだろうな。





そんなコーヒーと本と恋の思い出がカフェオーレのように詰まった特別な場所になったドルチェでわたしは最後の晩餐(おおげさ、しかも昼だし)を食べる。コーヒーをまず頼んで、ドルチェグラタンを食べてから、2杯目のコーヒーとパフェで〆るという順番も決めていた。飲み物は2杯目から半額になるという素晴らしきシステムがドルチェにはある。
そして今日はカウンターに座ろう。わたしは相変わらず読書のためにテーブル席ばかりだったので、近づいたようでまだ遠くの憧れていた喫茶店のカウンターに今日は座ろう。わたしにはずっとマスターに聞いてみたい店内の装飾のこともあった。今日はそのことも思い切って聞いてみよう。
そして今日はカウンターに座ろう。わたしは相変わらず読書のためにテーブル席ばかりだったので、近づいたようでまだ遠くの憧れていた喫茶店のカウンターに今日は座ろう。わたしにはずっとマスターに聞いてみたい店内の装飾のこともあった。今日はそのことも思い切って聞いてみよう。
到着して時計を見ると13時45分。店内は若い女性グループや何組かのお客さんで繁盛していた。マスターはちょうどカウンターの中でサイフォンでコーヒーを抽出していた。カウンターにはまだ誰も座ってはいない。マスターが忙しそうに動いているうちに、さっとわたしはカウンター席に座る。
「いらっしゃい、今日は一人だね」
「はい、実は前にお伝えした東京に行く日が明日なんです」
「おっと、ついに明日か。それは寂しいなあ。でも行く前に来てくれたんだね」
坂間さんと付き合うようになってから、ちょっとした恥ずかしさもあり読書会にもあまり顔を出せていなかった。一人ドルチェは月に数回相変わらず続けていて、マスターにはそれなりに坂間さんとの近況報告もしていた。東京にわたしが行ったり、彼が山梨に戻って来たり、なんだかんだ月に会えて2回くらいのペースをもう3年くらい続けていた。
「いらっしゃい、今日は一人だね」
「はい、実は前にお伝えした東京に行く日が明日なんです」
「おっと、ついに明日か。それは寂しいなあ。でも行く前に来てくれたんだね」
坂間さんと付き合うようになってから、ちょっとした恥ずかしさもあり読書会にもあまり顔を出せていなかった。一人ドルチェは月に数回相変わらず続けていて、マスターにはそれなりに坂間さんとの近況報告もしていた。東京にわたしが行ったり、彼が山梨に戻って来たり、なんだかんだ月に会えて2回くらいのペースをもう3年くらい続けていた。

見慣れたメニューの中から、今日はハニーブレンドをはじめて飲んでみようと思って注文した。マスターが落ち着くまでいつも通り本を読もうとカバンから読みかけの友部正人の「退屈は素敵」を取り出した。めくったページにサン=テグジュペリはもういない、と書いてある。
「どう、坂間くんには最近会えていないけど元気かい?」
わたしは本の世界に没頭していたけれど、ひと通りマスターが注文をさばいて少し余裕ができたタイミングで声をかけてくれた。
「はい、けっこう仕事忙しいみたいですよ」
「よかったねぇ。ここに来るようになったときはまだ駆け出しみたいな頃みたいだったけど、いつのまにか東京で写真の仕事で食べていけてるんだから」
「そうですね。わたしも写真の業界のことはよくわからないんですけど、いいご縁をいただいているみたいで。地方にいって撮影することも多いみたいです」
「カメラを持って地方を渡り歩くなんてうらやましいね。ぼくなんてこのカウンターからぜんぜん出られないんだから」
ドルチェを開いてから、どんなときも店を開け続けているマスターや奥さんはほんとうにすごい。わたしが働いているような会社システムの中では、誰か辞めたり体調不良で休んでも、誰かしら代わりがいて仕事は円滑にまわる。しかしドルチェのような個人店喫茶はマスターなしにはお店がまわらない。しかも休みが週に一度で朝早くから夜遅くまで店を開けているのだ。それを何十年も続けているすごさは、素人のわたしにもわかる。ほんとうに喫茶文化は尊い。
「はい、ハニーブレンド。はちみつは後入れだよ」そういって私の前に出されたカップ&ソーサーは、今日はシンプルな白。持ち手のところにさりげなくリボンの絵柄が描かれている。今日のわたしの服装からこのカップを選んでくれたのだろうか。はちみつを自分でコーヒーの中にそっと滴らす。コーヒーはいつも通りの顔をしているが、飲んで見るとコクのあるはちみつとのハーモニーが新鮮だった。
「マスター、今日はずっと聞いてみたかったことがあるんですけどいいですか」
そういって私はカウンターの食器棚の上に飾られてある詩を見上げた。
「その食器棚の上に書いてある詩とこのカウンターの上にもある詩がずっと気になっていて。誰の言葉なのか知りたくて」
「どう、坂間くんには最近会えていないけど元気かい?」
わたしは本の世界に没頭していたけれど、ひと通りマスターが注文をさばいて少し余裕ができたタイミングで声をかけてくれた。
「はい、けっこう仕事忙しいみたいですよ」
「よかったねぇ。ここに来るようになったときはまだ駆け出しみたいな頃みたいだったけど、いつのまにか東京で写真の仕事で食べていけてるんだから」
「そうですね。わたしも写真の業界のことはよくわからないんですけど、いいご縁をいただいているみたいで。地方にいって撮影することも多いみたいです」
「カメラを持って地方を渡り歩くなんてうらやましいね。ぼくなんてこのカウンターからぜんぜん出られないんだから」
ドルチェを開いてから、どんなときも店を開け続けているマスターや奥さんはほんとうにすごい。わたしが働いているような会社システムの中では、誰か辞めたり体調不良で休んでも、誰かしら代わりがいて仕事は円滑にまわる。しかしドルチェのような個人店喫茶はマスターなしにはお店がまわらない。しかも休みが週に一度で朝早くから夜遅くまで店を開けているのだ。それを何十年も続けているすごさは、素人のわたしにもわかる。ほんとうに喫茶文化は尊い。
「はい、ハニーブレンド。はちみつは後入れだよ」そういって私の前に出されたカップ&ソーサーは、今日はシンプルな白。持ち手のところにさりげなくリボンの絵柄が描かれている。今日のわたしの服装からこのカップを選んでくれたのだろうか。はちみつを自分でコーヒーの中にそっと滴らす。コーヒーはいつも通りの顔をしているが、飲んで見るとコクのあるはちみつとのハーモニーが新鮮だった。
「マスター、今日はずっと聞いてみたかったことがあるんですけどいいですか」
そういって私はカウンターの食器棚の上に飾られてある詩を見上げた。
「その食器棚の上に書いてある詩とこのカウンターの上にもある詩がずっと気になっていて。誰の言葉なのか知りたくて」




何度もドルチェに通ったことがある人なら絶対気になっていたであろう、店内に手描きされて掲示されている2編の詩。わたしは言葉の虫だ。初めてドルチェに足を踏み入れた時から、この2編の珈琲と人生(カウンター奥)、珈琲と恋愛(カウンター上)を描いたような言葉に心を掴まれていた。そのことはマスターと話せるようになっても言えずにいたし、お店の柱になっている言葉のような気がして気軽には聞けなかった。
「ああ、これね。もうずっと前の言葉だなぁ。この食器棚の上のはねえ、もう40年も前かなぁ、文藝春秋って雑誌があるでしょ。あの雑誌に載ってたのをメモしたんだよ。細かくは忘れちゃったけど遠藤周作さんが書いたものでね。この言葉には励まされたなあ」
冒頭には『コーヒーはそれを満たすための器をみつけるのに人生の伴侶を探し出すほどの熱情をもってしなければならない』と書いてある。もうそれだけでこのお店をあらわしているじゃないか、と思っていた。
「そっちはね、ぼくのオリジナル。恥ずかしいから説明はしないよ。まあ、きみたちみたいなことだよ。二人ともコーヒーが好きでしょ」
「やっぱり。こっちはマスターが書いたような、そんな気がしてたんですよ。そっかー、いい詩だなぁ」
自分の中で答え合わせができた。1杯のコーヒーにも、時によってそれぞれの物語が生まれることがある。失恋してその日店を訪れた人、なにか嬉しいことがあった人、恋人同士の初めてのデートの日、そしてなんてことのない普通の日にも。コーヒーはいつも変わらずわたしたちに寄り添ってくれている。少なくともわたしにとって、コーヒーというセピア色の液体と物語や言葉が綴られた本は、一生自分の身の回りから離れないものだと思う。
「今は山梨もコーヒーショップが増えてきたみたいだね。わたしの店は当初世界中のいろいろなコーヒーを知って味わってほしくてね。その中から自分のお気に入りをみつけてもらえればいいなと思ってたんだよ」
サイフォン式でコーヒーを淹れてくれるお店も今時なかなかめずらしい。古き良きお店に染み付いた空気感は長く続いているからこそノスタルジーを感じるものだ。そのノスタルジーは文化と言い換えてもいいと思う。こういうローカルの文化は、享受しているだけでは続かないはずだ。当たり前にいまここで、私の最後の晩餐(いいかげんしつこい)ができることに感謝しつつ、こういう文化を紡いでいるお店が山梨にもあることが誇らしい。わたしのコーヒー好きの友人に「すぐさまドルチェに行って」と店内の雰囲気やコーヒーを飲む時間の楽しさを伝えたこともある。
聞きたいことを聞いてマスターと雑談しながらドルチェグラタン(950円)をたいらげ、とっておきの抹茶パフェ(750円)を頼んだ。
「ああ、これね。もうずっと前の言葉だなぁ。この食器棚の上のはねえ、もう40年も前かなぁ、文藝春秋って雑誌があるでしょ。あの雑誌に載ってたのをメモしたんだよ。細かくは忘れちゃったけど遠藤周作さんが書いたものでね。この言葉には励まされたなあ」
冒頭には『コーヒーはそれを満たすための器をみつけるのに人生の伴侶を探し出すほどの熱情をもってしなければならない』と書いてある。もうそれだけでこのお店をあらわしているじゃないか、と思っていた。
「そっちはね、ぼくのオリジナル。恥ずかしいから説明はしないよ。まあ、きみたちみたいなことだよ。二人ともコーヒーが好きでしょ」
「やっぱり。こっちはマスターが書いたような、そんな気がしてたんですよ。そっかー、いい詩だなぁ」
自分の中で答え合わせができた。1杯のコーヒーにも、時によってそれぞれの物語が生まれることがある。失恋してその日店を訪れた人、なにか嬉しいことがあった人、恋人同士の初めてのデートの日、そしてなんてことのない普通の日にも。コーヒーはいつも変わらずわたしたちに寄り添ってくれている。少なくともわたしにとって、コーヒーというセピア色の液体と物語や言葉が綴られた本は、一生自分の身の回りから離れないものだと思う。
「今は山梨もコーヒーショップが増えてきたみたいだね。わたしの店は当初世界中のいろいろなコーヒーを知って味わってほしくてね。その中から自分のお気に入りをみつけてもらえればいいなと思ってたんだよ」
サイフォン式でコーヒーを淹れてくれるお店も今時なかなかめずらしい。古き良きお店に染み付いた空気感は長く続いているからこそノスタルジーを感じるものだ。そのノスタルジーは文化と言い換えてもいいと思う。こういうローカルの文化は、享受しているだけでは続かないはずだ。当たり前にいまここで、私の最後の晩餐(いいかげんしつこい)ができることに感謝しつつ、こういう文化を紡いでいるお店が山梨にもあることが誇らしい。わたしのコーヒー好きの友人に「すぐさまドルチェに行って」と店内の雰囲気やコーヒーを飲む時間の楽しさを伝えたこともある。
聞きたいことを聞いてマスターと雑談しながらドルチェグラタン(950円)をたいらげ、とっておきの抹茶パフェ(750円)を頼んだ。


甘いものを食べるのは、何か嬉しいことがあったときのドルチェでの楽しみにしている。しばらくこのパフェが食べれないなんて。そう思って、最近よく使っている父のおさがりのフィルムカメラでパフェを撮影した。現像してときおり見返そう。
坂間さんと付き合う前、最初のデートにこのフィルムカメラを持って行ったら坂間さんも同じカメラを持っていたと言った。坂間さんはその日はFUJIのX-pro1という最近のカメラを持ってきていて、お互いカメラをぶらさげて、春の釜無川を散歩しながら写真を撮りあった。わたしは撮られることはとても苦手だったのだけれど、坂間さんは初対面の時から変わらず、撮ったのかもわからないうちに撮影している。「スナップって身構えない感じがいいよね」と、どんなときでもテンション一定、飄々としていた。告白だって、わたしが東京に遊びに行った時に昼ご飯を食べた下北沢の王将で、2皿目の餃子を追加したあとに追加でビールも頼むんじゃないかというタイミングで「好きだから付き合ってくれないかな?」と言ってきたほどだ。わたしはまだ餃子が2個ほどお皿に残っていて、餃子と坂間さんを交互に見ながらとりあえず餃子をあと2個食べる間に考えて返事をした。なんで私のことを好きになったのかを聞いたら、本が好きで写真が好きで同郷でさらにドルチェの読書会にマスターに声かけられて来る人なら間違いないし初対面で写真を撮りたいなって思ったから、らしい。それなら他にも未婚の女子メンバーもいたし、言ってることの辻褄が合わないんじゃないかと思ったが、わたしもわたしで、本と写真とドルチェのコーヒーが好きで王将で告白してくる人なんて、わたしにとってはそれなりにしっくりくる状況だったので、餃子を2個食べたあとに「はい、お願いします」とご丁寧に返答した。
パフェと同時に〆の2杯目のコーヒーを頼むと、今度は見覚えのあるコーヒーカップで出てきた。わたしが初めてドルチェに訪れた時に出てきたコーヒーカップだった。その柄や色合いがとても印象的で、覚えていた。毎回コーヒーカップを変えてると後から気づいた時でも、たびたびこの柄でコーヒーがやってきた。
坂間さんと付き合う前、最初のデートにこのフィルムカメラを持って行ったら坂間さんも同じカメラを持っていたと言った。坂間さんはその日はFUJIのX-pro1という最近のカメラを持ってきていて、お互いカメラをぶらさげて、春の釜無川を散歩しながら写真を撮りあった。わたしは撮られることはとても苦手だったのだけれど、坂間さんは初対面の時から変わらず、撮ったのかもわからないうちに撮影している。「スナップって身構えない感じがいいよね」と、どんなときでもテンション一定、飄々としていた。告白だって、わたしが東京に遊びに行った時に昼ご飯を食べた下北沢の王将で、2皿目の餃子を追加したあとに追加でビールも頼むんじゃないかというタイミングで「好きだから付き合ってくれないかな?」と言ってきたほどだ。わたしはまだ餃子が2個ほどお皿に残っていて、餃子と坂間さんを交互に見ながらとりあえず餃子をあと2個食べる間に考えて返事をした。なんで私のことを好きになったのかを聞いたら、本が好きで写真が好きで同郷でさらにドルチェの読書会にマスターに声かけられて来る人なら間違いないし初対面で写真を撮りたいなって思ったから、らしい。それなら他にも未婚の女子メンバーもいたし、言ってることの辻褄が合わないんじゃないかと思ったが、わたしもわたしで、本と写真とドルチェのコーヒーが好きで王将で告白してくる人なんて、わたしにとってはそれなりにしっくりくる状況だったので、餃子を2個食べたあとに「はい、お願いします」とご丁寧に返答した。
パフェと同時に〆の2杯目のコーヒーを頼むと、今度は見覚えのあるコーヒーカップで出てきた。わたしが初めてドルチェに訪れた時に出てきたコーヒーカップだった。その柄や色合いがとても印象的で、覚えていた。毎回コーヒーカップを変えてると後から気づいた時でも、たびたびこの柄でコーヒーがやってきた。

「わたしってこのカップのイメージなんですか?」
「うーん、そうだね。たぶん一番最初もそのカップで出したんじゃないかな。いつでも格好や雰囲気がぶれないよね。そのへんは坂間くんとも同じ匂いを感じるよ。ぼくは最初からお似合いだと思ってたんだよな」
マスターはそう言って読書会で成立したカップルの名前をいく人かあげてくれた。そのたびにとてもマスターは嬉しそうな顔をする。
「東京はどこに住むんだい?」
「山梨に帰りやすいことも考えて中央線沿いがいいよねってなって、阿佐ヶ谷に住むことになりました」
坂間さんは練馬に住んでいたけど、わたしが山梨に帰りやすいことを理由に中央線推しで探して阿佐ヶ谷で二人暮らしのアパートを見つけた。阿佐ヶ谷にも「gion」という古き良き喫茶店がある。
「2人で帰ってきたらまた寄ってよね。そうそう、坂間くんにはお店があるうちにここの写真も撮ってほしいって頼んであるんだよ。早くしないと坂間くんが売れっ子になって撮ってもらえなくなっちゃうし、店だっていつまで続くかわからないんだからさ」
「そんなこと言わないでくださいよ。ドルチェがなくなったら困る人たくさんいますよ。わたしもその一人だし」
と言ったものの、東京に出たらなかなか足を運べなくなってしまうのも事実だ。
「とにかくお店がある限り、ぼくはお店でコーヒーを淹れ続けているから。東京で疲れたらいつでも帰っておいで」
マスターはそう言ってわたしに一冊の文庫本を手渡してくれた。タイトルを見ると獅子文六の「コーヒーと恋愛」という小説だった。
「餞別に。東京行く前に寄ってくれると思ってたからけっこう前から準備してたんだよ」
「嬉しい。ありがとうございます。じゃあ記念に」といって、差し出した本を受け取る前に持っていたカメラをマスターに向けてシャッターをおろした。
「さすが坂間くんの彼女だな」
「二番煎じですけど。ありがとうございます。大切に読みますね。また二人で寄ります」
わたしは最後のコーヒーを飲み終え、店内を名残惜しく見渡して会計を済ませて店を出た。明日は、東京へ。
「うーん、そうだね。たぶん一番最初もそのカップで出したんじゃないかな。いつでも格好や雰囲気がぶれないよね。そのへんは坂間くんとも同じ匂いを感じるよ。ぼくは最初からお似合いだと思ってたんだよな」
マスターはそう言って読書会で成立したカップルの名前をいく人かあげてくれた。そのたびにとてもマスターは嬉しそうな顔をする。
「東京はどこに住むんだい?」
「山梨に帰りやすいことも考えて中央線沿いがいいよねってなって、阿佐ヶ谷に住むことになりました」
坂間さんは練馬に住んでいたけど、わたしが山梨に帰りやすいことを理由に中央線推しで探して阿佐ヶ谷で二人暮らしのアパートを見つけた。阿佐ヶ谷にも「gion」という古き良き喫茶店がある。
「2人で帰ってきたらまた寄ってよね。そうそう、坂間くんにはお店があるうちにここの写真も撮ってほしいって頼んであるんだよ。早くしないと坂間くんが売れっ子になって撮ってもらえなくなっちゃうし、店だっていつまで続くかわからないんだからさ」
「そんなこと言わないでくださいよ。ドルチェがなくなったら困る人たくさんいますよ。わたしもその一人だし」
と言ったものの、東京に出たらなかなか足を運べなくなってしまうのも事実だ。
「とにかくお店がある限り、ぼくはお店でコーヒーを淹れ続けているから。東京で疲れたらいつでも帰っておいで」
マスターはそう言ってわたしに一冊の文庫本を手渡してくれた。タイトルを見ると獅子文六の「コーヒーと恋愛」という小説だった。
「餞別に。東京行く前に寄ってくれると思ってたからけっこう前から準備してたんだよ」
「嬉しい。ありがとうございます。じゃあ記念に」といって、差し出した本を受け取る前に持っていたカメラをマスターに向けてシャッターをおろした。
「さすが坂間くんの彼女だな」
「二番煎じですけど。ありがとうございます。大切に読みますね。また二人で寄ります」
わたしは最後のコーヒーを飲み終え、店内を名残惜しく見渡して会計を済ませて店を出た。明日は、東京へ。

東京に出たわたしは新宿の大型書店でまた書店員の仕事をはじめた。山梨にいる時よりも忙しなく、ときどき無性に落ちつかない。喫茶店もたくさんあるのに、あまり足を運べていない気がする。
山梨に住んでいる時に読んだ「夜空はいつでも最高密度の青色だ」の言葉が、また違った受け取り方で胸に迫ってきた。東京の夜空が曖昧な感情であふれた群青に見えるような時がある。それでもわたしは坂間さんとの二人暮らしが新鮮だ。ただひとつ、ドルチェのコーヒーが恋しい。あの空間で飲むコーヒーをわたしは欲しているんだ。次訪れた時にマスターはどのカップでコーヒーを淹れてくれるのだろう。
山梨に住んでいる時に読んだ「夜空はいつでも最高密度の青色だ」の言葉が、また違った受け取り方で胸に迫ってきた。東京の夜空が曖昧な感情であふれた群青に見えるような時がある。それでもわたしは坂間さんとの二人暮らしが新鮮だ。ただひとつ、ドルチェのコーヒーが恋しい。あの空間で飲むコーヒーをわたしは欲しているんだ。次訪れた時にマスターはどのカップでコーヒーを淹れてくれるのだろう。
年末も近づいた冬の寒さが本気を出してきた日、仕事帰りにスーパーで買い物を済ませ店を出てスマホを見ると以前ドルチェに行くのを薦めた山梨の友人からLINEが入っていた。彼女は新しいコーヒーロースターにも通いつつ、ドルチェにもマスターと話ができるくらいには通っているようだった。LINEには短文で「ドルチェ 2月で閉店」と書いてあった。彼女の性格を考えると、お店でマスターに直接か噂で聞いてすぐにわたしにLINEしてくれたに違いない。
坂間さんが帰ってきてからそのことを話すと「年末年始に山梨に帰ったら行こうね」とこんなときでもほんとうにぶれない平常心でこたえてくれた。わたしがいてもたってもいられない気持ちで「山梨にいたら毎週通うのに」と漏らすと、「俺も同じ気持ちだよ」と言って読書会で初めてわたしを撮ったカメラを部屋から引っ張り出してきた。「写真、撮らなきゃな」
そういってわたしの部屋着のままの姿をいつものようにパッと撮った。
「ドルチェの記録を残してね」
わたしたちが出会った珈琲専門店 ドルチェは40年の歴史に幕を閉じることになった。
年末はドルチェで甘くとりとめのない夢に浸りながら、2人で飲むコロンビアの甘さをめいっぱい感じよう。
坂間さんが帰ってきてからそのことを話すと「年末年始に山梨に帰ったら行こうね」とこんなときでもほんとうにぶれない平常心でこたえてくれた。わたしがいてもたってもいられない気持ちで「山梨にいたら毎週通うのに」と漏らすと、「俺も同じ気持ちだよ」と言って読書会で初めてわたしを撮ったカメラを部屋から引っ張り出してきた。「写真、撮らなきゃな」
そういってわたしの部屋着のままの姿をいつものようにパッと撮った。
「ドルチェの記録を残してね」
わたしたちが出会った珈琲専門店 ドルチェは40年の歴史に幕を閉じることになった。
年末はドルチェで甘くとりとめのない夢に浸りながら、2人で飲むコロンビアの甘さをめいっぱい感じよう。

珈琲専門店 ドルチェ
営業時間 / 9:00~23:00
TEL / 055-276-7281
月曜定休
この物語はお店の情報はすべてほんとうのことで、物語はフィクションです。
文:綾妹桐人