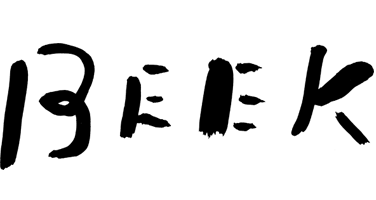これまでにも数々のユニークな本を作られてきた編集者の都築響一さんが「Neverland Diner 二度と行けないあの店で」という本を1月下旬に上梓した。
これは週刊メールマガジン『ROADSIDERS’
weekly』(有料)の巻頭連載として2017年から2020年までに掲載された文章を収録したものだ。
100人のさまざまなジャンルの著名人が綴った「二度と行けない店のエピソード」が辞書並みの厚みと重さと大きさの1冊にまとめられている。
他の本と平行読みしているので、読み終えるまでにはまだ時間がかかりそうな感じだけれど、そうでなくても、書き手によって文体もリズムも変わるので、少しずつ読み進めるのがこの本にはあっているような気がする。
これは週刊メールマガジン『ROADSIDERS’
weekly』(有料)の巻頭連載として2017年から2020年までに掲載された文章を収録したものだ。
100人のさまざまなジャンルの著名人が綴った「二度と行けない店のエピソード」が辞書並みの厚みと重さと大きさの1冊にまとめられている。
他の本と平行読みしているので、読み終えるまでにはまだ時間がかかりそうな感じだけれど、そうでなくても、書き手によって文体もリズムも変わるので、少しずつ読み進めるのがこの本にはあっているような気がする。
舌の記憶に残るような店も、そうじゃなかったことで記憶に残り続けている店も、どのエピソードにもグッと心をつかまれる。
そして「二度と行けない店」は、間違いなく年齢を重ねるほど増えてゆく。
私の中にもそんな店がもはやひとつや二つではなく、書き連ねたら結構な数になるだろう。
そして「二度と行けない店」は、間違いなく年齢を重ねるほど増えてゆく。
私の中にもそんな店がもはやひとつや二つではなく、書き連ねたら結構な数になるだろう。
不意に思い出した、ビルのエレベーターが骨董品級の古さの手動式で、レーズンバターがおいしかった銀座の地下の老舗のバーのこと。
バルセロナの小さな広場の片隅の2階にあって、常連しか入れないその不思議な店で時々かかっていた、マイルス・デイヴィスがカバーした“Time after time”を聴いた夜のこと。
おばあちゃんとおじいちゃんが二人でやっていた甲府中心街にあった小さな食堂「田中家」さんで夏の昼休憩にいつも食べていた、安くて具が盛りだくさんの冷やし中華など、ひとつ思い出すごとに、次から次へと芋づる式に記憶の扉が開かれてゆく。
バルセロナの小さな広場の片隅の2階にあって、常連しか入れないその不思議な店で時々かかっていた、マイルス・デイヴィスがカバーした“Time after time”を聴いた夜のこと。
おばあちゃんとおじいちゃんが二人でやっていた甲府中心街にあった小さな食堂「田中家」さんで夏の昼休憩にいつも食べていた、安くて具が盛りだくさんの冷やし中華など、ひとつ思い出すごとに、次から次へと芋づる式に記憶の扉が開かれてゆく。



コロナで予想もしていなかったこんな社会情勢となった現在、行きたいと思っていた店も私が知らぬ間に静かに姿を消してゆくのだろう。
そして書きながら、二度と行けない店の記憶の多さにちょっと驚いている。人はそんな儚いかけらの記憶ばかりでできているのではないのか。
そして書きながら、二度と行けない店の記憶の多さにちょっと驚いている。人はそんな儚いかけらの記憶ばかりでできているのではないのか。
生まれ故郷の小さな町で私が子ども時代に一番多く行ったのは、商店街の四つ角にあった食堂「かど」だった。
我が家は洋食というものを好まなかった父と、東京から嫁にきた洋食好きだった母と、私と弟もみんな好みが違うので、当時一家揃って唯一行けた町内の店が「かど」だった。いわゆる中華と丼ものがある大衆食堂だ。うちは常にお金が無かったから、外食と言ってもハンバーグなんかが食べられるレストランよりも値段が安い食堂ばかりだったのだ。
我が家は洋食というものを好まなかった父と、東京から嫁にきた洋食好きだった母と、私と弟もみんな好みが違うので、当時一家揃って唯一行けた町内の店が「かど」だった。いわゆる中華と丼ものがある大衆食堂だ。うちは常にお金が無かったから、外食と言ってもハンバーグなんかが食べられるレストランよりも値段が安い食堂ばかりだったのだ。
父はいつも味噌ラーメンを注文し、母と私は醤油ラーメンを注文した。弟が食べていたものは何だったかは思い出せない。
おいしかったどうかの記憶は私の舌には残っていないけれど、たしか子どもには多すぎて、いつもものすごく頑張って食べていた。食べられなかった時は、父ではなく母がもったいないからと言って食べていた。母は私たちが残すたび、「残り物食べてばかりだから太るのよ」とぼやいていた。
おいしかったどうかの記憶は私の舌には残っていないけれど、たしか子どもには多すぎて、いつもものすごく頑張って食べていた。食べられなかった時は、父ではなく母がもったいないからと言って食べていた。母は私たちが残すたび、「残り物食べてばかりだから太るのよ」とぼやいていた。
父はもともと人のいるところがそんなに好きではなくて、外食よりも家で出前を食べる方が落ち着くような人だった。私は子どもの頃、そんな父をなんてつまらないのだろうと思っていた。
私は外で食べるごはんの特別感と高揚感が大好きで、知らない店ならなおさらどきどきしてうれしいと思うような子どもだった。
私は外で食べるごはんの特別感と高揚感が大好きで、知らない店ならなおさらどきどきしてうれしいと思うような子どもだった。
ある日の休日、珍しく家族で電車で出掛けたその帰り、「夕飯を作るのも面倒だから「かど」で食べて帰ろう」と母が言い出した。
父もいつもは付き合って食べてくれていたのだが、その日の父はせっかくの休みを家族に付き合わされて疲れたのか、駅からの道中も「出前を頼めばいいじゃないか」と言って聞かなかった。
とうとう「かど」に着いて、私と弟を先頭に店の扉を開けて入って私が振り向いた時、「俺はひとりで家で出前を頼んで食べるからいい」と父は背中を向けて家の方向に歩き出してしまった。
母はもちろん怒り心頭だった。「いつだって勝手なんだから!」と言い捨てた。
私は両親を心の底から恥ずかしいと思った。店まで来ているのに一人分だけ出前を頼むという父の行為も、それに怒る母の醜態も。ああ、なんて最悪なんだと思った。
父もいつもは付き合って食べてくれていたのだが、その日の父はせっかくの休みを家族に付き合わされて疲れたのか、駅からの道中も「出前を頼めばいいじゃないか」と言って聞かなかった。
とうとう「かど」に着いて、私と弟を先頭に店の扉を開けて入って私が振り向いた時、「俺はひとりで家で出前を頼んで食べるからいい」と父は背中を向けて家の方向に歩き出してしまった。
母はもちろん怒り心頭だった。「いつだって勝手なんだから!」と言い捨てた。
私は両親を心の底から恥ずかしいと思った。店まで来ているのに一人分だけ出前を頼むという父の行為も、それに怒る母の醜態も。ああ、なんて最悪なんだと思った。
私は当時11歳か12歳くらいだったと思う。映像として鮮明に記憶しているくらいだから、あの日の事件は相当嫌だったのに違いない。
たぶんあんなに食べに行っていた「かど」へ行ったのは、それが最後だったように思う。それ以降の「かど」の記憶というものが全くないからだ。
その後知らぬ間に食堂「かど」は無くなってしまった。
たぶんあんなに食べに行っていた「かど」へ行ったのは、それが最後だったように思う。それ以降の「かど」の記憶というものが全くないからだ。
その後知らぬ間に食堂「かど」は無くなってしまった。
今自分の本屋からは、「かど」が当時あった駐車場になっているその場所が斜め向かいに見える。
こんなに小さかったっけ?と思うくらい狭い敷地を通り過ぎても、もう思い出したりすることは正直無かった。それが都築響一さんの”Neverland Diner”を読んだら、不意に思い出してしまった。
家族の気持ちが少しずつバラバラになっていったあの頃。あの日のラーメンは、幸福な食事とは言えなかったけれど、それが無かったら私は15で家を出ようとは思わなかったかもしれないし、それが無かったら本屋で働いている今の人生があるとも思えない。
きっと良かったのだ。
それですべて良かったのだ。
こんなに小さかったっけ?と思うくらい狭い敷地を通り過ぎても、もう思い出したりすることは正直無かった。それが都築響一さんの”Neverland Diner”を読んだら、不意に思い出してしまった。
家族の気持ちが少しずつバラバラになっていったあの頃。あの日のラーメンは、幸福な食事とは言えなかったけれど、それが無かったら私は15で家を出ようとは思わなかったかもしれないし、それが無かったら本屋で働いている今の人生があるとも思えない。
きっと良かったのだ。
それですべて良かったのだ。
[BOOK LIST]

『Neverland Diner 二度と行けないあの店で』
編者:都築響一 編集:臼井悠
装丁:渋井史生(PANKEY)
出版:ケンエレブックス
ここに記された100人の忘れられない店の記憶は、他人の記憶でありながら、時に自分の記憶と重なって、忘れていた風景を思い出させてくれたりもします。
失われた店やモノというのは、その姿を消すことで、ずっと印象深く記憶に刻まれるような気がします。