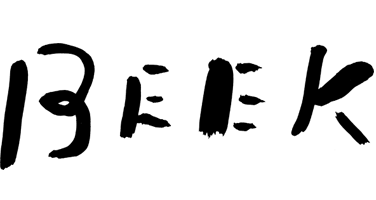伊丹さんの「人称代名詞における自我とは何か」という問いから生まれた「僕」や「あなた」などの人称を極力省略しない独自の翻訳文体も、この小説を他とは違った印象的なものにしている。 63の単語からなる各章のタイトルも、本・海・月・ポットなど、その単語の羅列がまるでスクラブルという英語のボードゲームのようでもあり、実際小説の中にも言葉遊びのような会話をするシーンが登場している。

物語は10歳の少年ピートが、誕生日に小説家の父から新しい本と「自分の小説を書く」という仕事を与えられるところからはじまる。 それは誰のためでもなく、本人が世界と自分を知るために書くことのきっかけでもあった。 この海辺の町で暮らす小説家の父と息子の、日々の暮らしを描いた物語は、二人の対話が中心となって続いてゆく。 二人で歩いた海辺で見つけた小石や流木をよく観察すること、簡単だけどおいしい料理のこと、世界について。時に哲学的で、時にユーモアのある会話が交わされる。
10代で初めて読んだときは、後々自分が親になるとは想像もしなかったけれど、ここに描かれていたような、お互いを認め合い、対等に話すことのできる風通しのよい親子関係を好ましく思った。そしてこんな親子に憧れた。今でも娘とは、そんな間柄でありたいと思うほど、この小説の影響は大きい。

そしてこの小説を読むと思い浮かぶ風景が、ジョエル・マイヤーウィッツの「ケープ・ライト」という写真集に出てくる海辺の風景だ。
サローヤンの小説の舞台はアメリカ西海岸、マイヤーウィッツの写真集は東海岸で撮影されたもなので場所は全く異なるのだけれど、葉山の海も含めてそこに流れている空気なのか光なのか、私の中で不思議と一本の線のような共通項を感じる。 ページをめくりながら、波の音や風を想像してみる。 それでもやっぱり、そのうち自由な移動ができるようになったら、本物の海が見たいなぁと心から思う。その時も本を片手にビールを持って。
[BOOK LIST]

「パパ・ユーア・クレイジー」(ウイリアム・サローヤン、伊丹十三訳/ブロンズ新社)
最初に読んだのは新潮文庫版でした。文庫はどこに置いたのか家でなかなか見つけられなかったのでここには復刻版の写真を。いくつかの版が出版されていたのですが、今は古本でしか手に入らなくなってしまったのが残念です。

「CAPE LIGHT」(Joel Meyerowitz/洋書)
ジョエル・マイヤーウィッツは、他にも夏の風景を撮った「A SUMMER’S DAY」という写真集をはじめ、どれもとても良いです。1938年生まれだから、気づけば今年82歳なのですね。