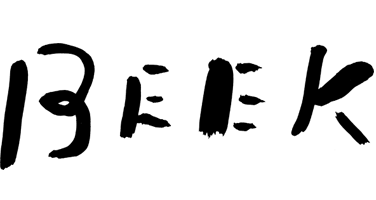こんなふうに感じたことは、今まで生きてきてこの春が初めてだったかもしれない。
世界が小さく感じられる理由はもちろん、新型コロナウイルスのせいである。1月には、まだまだ遠い国での話みたいに思っていた私たちのことを、ウイルスはまるで嘲笑うかのように、いつの間にかすごい速度で世界中に蔓延し、今や南極以外のすべての大陸を覆い尽くしている。
日々ウイルスの脅威にさらされ、マスクや除菌アルコールで身を守るような現実が、こんなにも暴力的にやって来るなんて想像したこともなかった。
世界はいつだって広くて大きかったはずなのに、今ではみんなが同じ敵と向き合っている。

それを自分の身に置き換えると、今まで当たり前のようにできていたことが出来なくなってしまった。
おいしいごはんを友人と食べに行く、おしゃべりをする、お酒を飲みに行く、旅行に行く、美術館へ行く、映画館へ行く、コンサートへ行く、温泉に行く、図書館へ行く、もはや山小屋へも行けないと聞いた。
そんなごくあたりまえの事ができなくなる日常が来るなんて。
国内外どこへでも自由に旅に行きたい、自分の本屋を開けてお客さんといろんな話がしたい、マスクなしで仕事したい。

意味は、「あまりに身近すぎて、必要不可欠なもののありがたみが薄れているさま。
魚にとっての水、人間にとっての空気のように、当たり前のような存在で意識することがなく、大切さが分からないことから」だそうだ。
今では「家」はシェルターのように、守られた安全な場所だと感じることができる。ここにいればマスクもいらない。読みたい本も山ほどある。

今や「家」の時代である。
(だけど「家」という場所が、苦痛に満ちた人だって間違いなくいるだろう。それを思うと本当に悲しくなる。逃げ場や行き場を失って苦しんでいる人々は今、どうやって過ごしているのだろう。)
倹約につとめ、たまった本を読み、料理を作り、音楽を聴き、体を動かし、粛々と日々を過ごそう。誰もがいつどこで感染しても不思議ではない日々に、それぞれができることをし、今を生き抜くのだ。
この困難の先に、全く異なる価値観が開けたり、人が生きるうえでの本質や、根本的なことが大切にされる未来に繋げてゆけると信じたい。
[BOOK LIST]

「シェイクスピア&カンパニー書店の優しき日々」(河出書房新社/2020年に文庫化)
家にいながら、パリに実在するちょっと変わった書店へ読書の旅をしてみるのはどうだろう。
この本は、90年代の終わりにパリへ渡ったカナダ人の新聞記者ジェレミーが、ひょんなことから住み着くことになった伝説の本屋「シェイクスピア&カンパニー書店」での日々を描いた、まるで映画みたいな本当の話。
店主は、アメリカからパリに流れ着いて二代目となった、風変わりで一癖も二癖もあるアメリカ人、ジョージ・ホイットマン氏。 ヘンリー・ミラーやウィリアム・バロウズ、アレン・ギンズバーグなど名だたる作家が出入りし、朗読会が開かれ名物書店となった。 他にも彼は、「見知らぬ人も、変装した天使かもしれないから冷たくするな」というモットーのもと、書店の一角に物書きや旅の若者に無償で宿と食事を提供してきた。 この書店も、緊急時の「家」と同様、シェルターのようにそんな迷える人々を庇護する場所だった。 現在も、ホイットマン氏亡き後も娘のシルヴィアさんが意思を引き継ぎ運営されているという。
この本を読んでいると、まるで自分もシェイクスピア&カンパニー書店の住人になったような気持ちになれる。 ここはいつか訪れてみたい本屋でもあり、たとえ願いが叶わなかったとしても、心のどこかにずっと持ち続けていたいと思うような、様々な人に開かれた「本屋のユートピア」なのである。