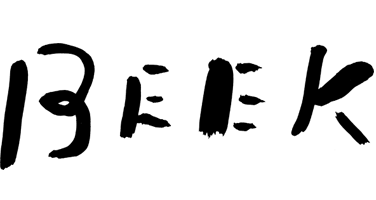他に書きかけの文章もあったのに、なんとなくまとまらなくて完成できずにいたら、この4月、桜もこぶしも雪柳も満開の美しい春の日の午後に、年老いた父が他界した。
こういうことはあまりにも私的なことすぎるので、連載に書くことがためらわれていたのだけれど、他のことを書こうと思ってもどうしても引っかかってしまって、それを書かずには前に進めなくなってしまった。なのでここに書くことを、どうか許していただけたらと思う。
こういうことはあまりにも私的なことすぎるので、連載に書くことがためらわれていたのだけれど、他のことを書こうと思ってもどうしても引っかかってしまって、それを書かずには前に進めなくなってしまった。なのでここに書くことを、どうか許していただけたらと思う。

4月21日、私がアメリカヤの自分の本屋で、その日最初のお客さんと話し終わってのんびり本を眺めていたら、父が入院していた病院から容体が急変したと呼び出しの電話があった。
病院に着いてからわずか1時間ばかりだったけれど、私が父の手を握りながら、夫と娘と3人で、父の最後の呼吸が部屋の空気に溶けてゆく瞬間まで見届けることができた。
苦しむことも、呻くこともない実に静かで穏やかな、なんとも父らしい旅立ちだった。
病院に着いてからわずか1時間ばかりだったけれど、私が父の手を握りながら、夫と娘と3人で、父の最後の呼吸が部屋の空気に溶けてゆく瞬間まで見届けることができた。
苦しむことも、呻くこともない実に静かで穏やかな、なんとも父らしい旅立ちだった。
私の父は特別子煩悩でもなかったし、かといって厳格でもなかった。家庭においても「孤独」というものと常に共存しているような、物静かで主張をしない父だった。
これまでにも大切な友人や祖父や知人を何人も見送って来たけれど、肉親の死というものは、こんなにも複雑で特別なものなのかと、父を失ってその感覚を初めて知った。
これまでにも大切な友人や祖父や知人を何人も見送って来たけれど、肉親の死というものは、こんなにも複雑で特別なものなのかと、父を失ってその感覚を初めて知った。
今ではだいぶ少なくなってきたけれど、信号待ちなどでなんとなく空を見あげる時や、ぼんやり気の抜けるような瞬間、父と過ごした記憶の扉がふと開く。その度にむやみやたらに視界が涙で滲んできて、まだまだ心が癒えていないのだと体の反応によって気づかされる。
かといって年老いて、人生を全うして亡くなった父を思う時、悲しいのかと言われれば、それともまた違う気持ちに包まれている。
かといって年老いて、人生を全うして亡くなった父を思う時、悲しいのかと言われれば、それともまた違う気持ちに包まれている。

もう8年以上経つだろうか。何を贈ったところで、たいして喜ぶこともなくなってしまった父が心身ともに元気なうちに、とにかく手紙を書かなくてはという気持ちになり、8月11日の父の誕生日に、生まれて初めて父に宛ててちゃんとした手紙を書いて渡したことがあった。
20歳の時に父から生まれてはじめてもらった手紙のお礼を、もう一度きちんと伝えたいと思ったのだ。
20歳の時に父から生まれてはじめてもらった手紙のお礼を、もう一度きちんと伝えたいと思ったのだ。
それは当時、19歳の時に母に勘当されて日本を飛び出して、バルセロナに暮らしていた私が20歳になっていた秋のことだった。私は父から一通の手紙を受け取った。
手紙にはたわいのない近況と、成人おめでとうということと、いつでも帰って来てください、ということが父の特徴のある、線が細くてさらさらとした達筆な文字で綴られていた。
エアメールの宛名の書き方など、父がそれをどうやって調べたのか今でも不思議なくらいだが、父がどうしても私に伝えたかったこと、伝えなくてはならないのだという思いが、その行為から伝わってきた。
その行為の純粋さに心を打たれて、私は手紙を読みながら涙が止まらなかったことを思い出す。
手紙にはたわいのない近況と、成人おめでとうということと、いつでも帰って来てください、ということが父の特徴のある、線が細くてさらさらとした達筆な文字で綴られていた。
エアメールの宛名の書き方など、父がそれをどうやって調べたのか今でも不思議なくらいだが、父がどうしても私に伝えたかったこと、伝えなくてはならないのだという思いが、その行為から伝わってきた。
その行為の純粋さに心を打たれて、私は手紙を読みながら涙が止まらなかったことを思い出す。

私が最後に父に渡したその手紙を、父がどんな気持ちで読み、どんな風に思ったのかは結局聞けずじまいだったけれど、おそらく父なりに喜んでくれたのではないかと思う。
その手紙を渡した後年、父は脳梗塞で倒れ、ことあるごとに入退院を繰り返していたので、あの時手紙を読んでもらえて本当に良かったと今でも思う。
その手紙を渡した後年、父は脳梗塞で倒れ、ことあるごとに入退院を繰り返していたので、あの時手紙を読んでもらえて本当に良かったと今でも思う。
父の死を通して、私は実に多くのことを学んだ。菩提寺である真言宗のお寺の住職と、長いこと疎遠だった弟と一緒に相談しながら父の戒名をつけられたことも、父との絆を深めるような行いだった。
山歩きが好きだった父の戒名には、父の名前から「和」の字を、そして「山」という字を入れて「慈観和山居士(じかんわさんこじ)」とした。
そして父のその戒名が、祖父母の戒名からまったく偶然にもそれぞれ一文字ずついただいていたことにも不思議なつながりを感じた。
山歩きが好きだった父の戒名には、父の名前から「和」の字を、そして「山」という字を入れて「慈観和山居士(じかんわさんこじ)」とした。
そして父のその戒名が、祖父母の戒名からまったく偶然にもそれぞれ一文字ずついただいていたことにも不思議なつながりを感じた。

毎朝、父の形見の自動巻の腕時計をつける時、その冷んやりとした重さに触れるたび、父の姿を思い浮かべる。
腕時計に耳を当てると小さく聞こえてくるその音は、時計が刻む「時の証」だ。
父を送り出したことで、人生には必ず終わりがあるということを、ますます強く意識するようになった。
「生きる」ということに、私はもうぼんやりとはできなくなってしまった。
腕時計に耳を当てると小さく聞こえてくるその音は、時計が刻む「時の証」だ。
父を送り出したことで、人生には必ず終わりがあるということを、ますます強く意識するようになった。
「生きる」ということに、私はもうぼんやりとはできなくなってしまった。
[BOOK LIST]

「詩ふたつ」/長田弘
この本は、詩人の長田弘さんが亡き妻の思い出に捧げた詩集です。
「花を持って、会いにゆく」「人生は森の中の一日」という二つの詩と、グスタフ・クリムトの樹木と花々の挿絵からなっています。
長田さんがあとがきで語っている「喪によって、人が発見するのは絆なのだ」という、言葉のその確かさが深く心に沁み入ります。
2010年に初めてこの本を手にして以来、喪失という感情に木陰のように寄り添ってくれるこの詩集は、私にとって特別な一冊です。