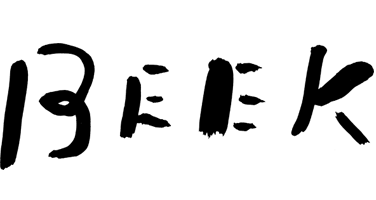春は気持ちがざわざわする。
世間では卒業式も終わり、学生たちもまばらになった静かな通勤電車に揺られていたら、中学を卒業して初めて親元を離れた15の春を思い出していた。
地元長野の高校には進学せず、寮のある埼玉の高校へ行くことが決まった時、私の気持ちは晴々としていた。
親元を離れる寂しさなんて微塵もなく、気持ちはとうに家族や兄弟や仲の良かった同級生からすらも離れていた。
唯一離れがたく、目に焼き付けて置こうと思ったのは、物心ついた時からそこにあった八ヶ岳や山々の風景だった。
世間では卒業式も終わり、学生たちもまばらになった静かな通勤電車に揺られていたら、中学を卒業して初めて親元を離れた15の春を思い出していた。
地元長野の高校には進学せず、寮のある埼玉の高校へ行くことが決まった時、私の気持ちは晴々としていた。
親元を離れる寂しさなんて微塵もなく、気持ちはとうに家族や兄弟や仲の良かった同級生からすらも離れていた。
唯一離れがたく、目に焼き付けて置こうと思ったのは、物心ついた時からそこにあった八ヶ岳や山々の風景だった。

私が生まれ育った町には、当時はまだ学校以外に図書館もなく、小さな本屋が1軒あるだけだった。小学生の時から、マンガ以外の本だったら欲しいと言えば母がためらわずに買ってくれたこともあって、その本屋に通い詰め、自然と本の虫になった。
そのうち本からはじまって音楽にも映画にも興味を持つようになり、大事な情報源だった雑誌をいろいろ買うようになってからは、興味の対象はますます広がっていった。
紙面を見ているだけで、広い世界に心踊る時代。けれど自分の中に世界が広がると同時に、学校にも田舎にも退屈さと窮屈さを感じるようになってしまった。同級生と話していても、いつもどこか満たされない。
映画や音楽や本から単純に「アメリカンカルチャー」に憧れた私は、そのうち本屋で手にした数冊のアメリカ留学記を読んで、親のお財布事情なんて考えることもなく、中学を卒業したらアメリカの高校へ進学する道を考えはじめた。
家から通える地元の高校への進学も、全く考えなかったわけではないのだけれど、一度「家を出たい」という気持ちにとりつかれてしまってからは、もう歯止めが効かなかった。
コツコツ資料を集め、親に留学試験を受けに東京に行きたいと言うと、落ちたらあきらめもつくだろうと思ったのか、意外にも試験を受けさせてくれた。学芸大学駅近くの事務局での面接にも同行してくれた。
結果は合格だった。今思えば語学力よりもメンタルがタフそうだと思われたのが功を奏したのだと思う。
けれど、残念ながらその頃はまだ、アメリカの高校での単位も卒業資格も日本では認められないという、今では考えられないような時代で、日本の高校にまた通い直すならお金がかかるからそんな留学は許可できない、と親に猛反対され、この話は白紙に戻ってしまった。
この時に、娘を海外にぽーんと送り出してくれる裕福で豪快な味方が欲しいと心底思った。この時はひとりで大泣きして諦めるしかなかった。
その後、進路に関してどうしようかと悩んでいるうちにどんどん日々は過ぎて行き、私は本当に焦っていた。
そんな時たまたま新聞で、反競争主義と個性尊重を基本に自由な心を育む教育を掲げた、まだ開校1年にも満たないユニークな学校について書かれた一冊の本に巡り会った。
すぐにその本を行きつけの書店で取り寄せて一気に読み終え、日本で高校に行くのならここしかない、ここで学んでみたいと強く思った。その時はすでに願書の締め切りまで2週間くらいしかなかったはずだ。
両親の話をまたもや聞かず、強引に願書を出すまでにこぎつけた。とにかく必死だった。思い込みが激しい10代は、その世界が狭い分、自分勝手でまっすぐなのだ。
筆記テストと面接と表現活動と、授業を受けて感想文を書くなどの試験を終え、その強すぎる思いが天にも通じたのか、その高校に念願叶って無事合格することができた。
自分にとってはまさに人生の春である。
もうこうなったら親には申し訳ないが、あらゆる手段を講じて地元への進学を拒むしかない。公立の受験日、私は真っ白なまま回答用紙を提出した。
カリカリと他人の鉛筆の音だけが響きわたる教室で、壁の時計をじっと見ながらそれからやり過ごさなければならない波乱の日々のことを考えていた。
当然、公立の合格発表に私の名前はない。「頑張ったけどだめだったよ」という私に母親は、「これからどうするの」と責めたてた。険悪な話し合いだった。
「大学へは行かせてもらえなくてもいいから、どうか行かせて欲しい」と懇願した。
それまでじっと聞いていた無口な父親がぼそっとひとこと言った。「仕方ないだろ。埼玉に行くしか。」そんな言葉を言わせてしまったことを、ほんの少し申し訳ないと思いながらも本当にありがたかった。
そして晴れて私の進路は決まったのだ。
それは、自分の人生を初めて手に入れた日であると同時に、初めて自分の選択に責任を負うという覚悟を決めた日でもあった。
そのうち本からはじまって音楽にも映画にも興味を持つようになり、大事な情報源だった雑誌をいろいろ買うようになってからは、興味の対象はますます広がっていった。
紙面を見ているだけで、広い世界に心踊る時代。けれど自分の中に世界が広がると同時に、学校にも田舎にも退屈さと窮屈さを感じるようになってしまった。同級生と話していても、いつもどこか満たされない。
映画や音楽や本から単純に「アメリカンカルチャー」に憧れた私は、そのうち本屋で手にした数冊のアメリカ留学記を読んで、親のお財布事情なんて考えることもなく、中学を卒業したらアメリカの高校へ進学する道を考えはじめた。
家から通える地元の高校への進学も、全く考えなかったわけではないのだけれど、一度「家を出たい」という気持ちにとりつかれてしまってからは、もう歯止めが効かなかった。
コツコツ資料を集め、親に留学試験を受けに東京に行きたいと言うと、落ちたらあきらめもつくだろうと思ったのか、意外にも試験を受けさせてくれた。学芸大学駅近くの事務局での面接にも同行してくれた。
結果は合格だった。今思えば語学力よりもメンタルがタフそうだと思われたのが功を奏したのだと思う。
けれど、残念ながらその頃はまだ、アメリカの高校での単位も卒業資格も日本では認められないという、今では考えられないような時代で、日本の高校にまた通い直すならお金がかかるからそんな留学は許可できない、と親に猛反対され、この話は白紙に戻ってしまった。
この時に、娘を海外にぽーんと送り出してくれる裕福で豪快な味方が欲しいと心底思った。この時はひとりで大泣きして諦めるしかなかった。
その後、進路に関してどうしようかと悩んでいるうちにどんどん日々は過ぎて行き、私は本当に焦っていた。
そんな時たまたま新聞で、反競争主義と個性尊重を基本に自由な心を育む教育を掲げた、まだ開校1年にも満たないユニークな学校について書かれた一冊の本に巡り会った。
すぐにその本を行きつけの書店で取り寄せて一気に読み終え、日本で高校に行くのならここしかない、ここで学んでみたいと強く思った。その時はすでに願書の締め切りまで2週間くらいしかなかったはずだ。
両親の話をまたもや聞かず、強引に願書を出すまでにこぎつけた。とにかく必死だった。思い込みが激しい10代は、その世界が狭い分、自分勝手でまっすぐなのだ。
筆記テストと面接と表現活動と、授業を受けて感想文を書くなどの試験を終え、その強すぎる思いが天にも通じたのか、その高校に念願叶って無事合格することができた。
自分にとってはまさに人生の春である。
もうこうなったら親には申し訳ないが、あらゆる手段を講じて地元への進学を拒むしかない。公立の受験日、私は真っ白なまま回答用紙を提出した。
カリカリと他人の鉛筆の音だけが響きわたる教室で、壁の時計をじっと見ながらそれからやり過ごさなければならない波乱の日々のことを考えていた。
当然、公立の合格発表に私の名前はない。「頑張ったけどだめだったよ」という私に母親は、「これからどうするの」と責めたてた。険悪な話し合いだった。
「大学へは行かせてもらえなくてもいいから、どうか行かせて欲しい」と懇願した。
それまでじっと聞いていた無口な父親がぼそっとひとこと言った。「仕方ないだろ。埼玉に行くしか。」そんな言葉を言わせてしまったことを、ほんの少し申し訳ないと思いながらも本当にありがたかった。
そして晴れて私の進路は決まったのだ。
それは、自分の人生を初めて手に入れた日であると同時に、初めて自分の選択に責任を負うという覚悟を決めた日でもあった。

寒さが徐々にやわらいで、草や土の匂いが感じられるようになってくると、今年もいつの間にか春がそっとやって来ている。いつもよりからっぽの電車やそわそわした周りの空気のせいで、こんな風に遠い昔のことをはっきりと思い出してしまったりする。
今でも春は気持ちがざわざわする。
今年はいろいろなことが大きく変わってゆくだろう。
今でも春は気持ちがざわざわする。
今年はいろいろなことが大きく変わってゆくだろう。

[BOOK LIST]
「ぼくの伯父さん」/伊丹十三(つるとはな)
俳優、エッセイスト、映画監督など多才な人生を生きた伊丹十三さんの没後20年を機に、昨年末出版された単行本未収録のエッセイを集めた本。仕事から育児まで、世の中の常識にとらわれないユニークな視点で書かれた言葉には、いつの時代にも見失いたくない本質が詰まっている。これから新しい生活をはじめる人にも贈りたい一冊。
「パパ・ユーア・クレイジー」/ウィリアム・サローヤン(絶版/古書のみ)
マリブの海辺で暮らしはじめた作家の父と10歳の息子が日々の中で人生とは何か、世界を理解するために大切なことについて語り合い、探してゆく物語。この本の中の、互いを認め合う大人と子どもがいい意味で対等な関係性は、共感するところであり、伊丹十三さんの主語にこだわった独特の翻訳もこの小説を特別な一冊にしているような気がします。